生物多様性は「生態系の多様性」「種の多様性」「遺伝子の多様性」この3つからできています。
自然と生物多様性の豊かさを測る指数「生きている地球指数(LPI)]によると、1970年と2020年に計測した生物の密度を比べた結果、脊椎動物の数が68%減少していることが分かりました。
生きている地球レポート2024 – 自然は危機に瀕している – |WWFジャパン
3つの多様性を意識しよう
生物多様性は、ただ生き物の数がたくさんいれば良いということではなく、次の3つの多様性をずっと守り続けていくことが大切です。
1.種の多様性
生物と言っても虫や魚や鳥だけでなく植物やキノコなどの菌類も同じ生物に含まれます。また、虫といってもその中にはいくつもの種類があります。例えば、虫の「チョウ」は日本の中だけでもに260種類以上いるとされています。これら1つ1つの種が大切でかけがえのないもので、たくさんの種類がいることを種の多様性と言います。
2.遺伝子の多様性
同じ種類の生き物でもそれぞれに個性があります。例えば同じ「アサリ」という生き物でも性別の違いや模様、性格などが違ってくるという、それぞれに個性を
持っています。これにより環境の急な変化が起こっても絶滅しにくくなり子孫を残していきやすくなるのです。これこそが遺伝子の多様性と言います。
3.生態系の多様性
生態系とは言わば、自然を取り巻く環境のこと。例えば、木々が生い茂る「森」が住みやすいという生き物もいれば、雨が少なくて気候が乾燥している「砂漠」が住みやすいという生き物、はたまた水で満たされている「海」が住みやすいという生き物がいたりと、それぞれの生き物にとって住みやすい場所がたくさんあります。それこそが生態系の多様性と言います。

以上が生物多様性を作っている3つの多様性になります。
地球上に生命が誕生してから40億年。その間、それぞれの生物が食べたり食べられたり時には共生したりと、複雑に組み合わさっていることで今の豊かな生物多様性が保たれてきました。
失われつつある生物多様性
しかし、そんな生物多様性が、自然と生物多様性の豊かさを測る数値「生きている地球指数(LPI)」によると、1970年から2020年までの50年間で73%も減少してしまいました。このLPIは、5,495種の野生の脊椎動物(両生類、鳥類、魚類、哺乳類、爬虫類)における、約3万5,000の個体群に対する分析に基づき、ロンドン動物学協会が作成しました。
出典 WWFジャパン
このまま絶滅が進行すると複雑に組み合わさることで保たれていた生物多様性が単純な組み合わせになってしまい、長い年月をかけて作られた生物多様性が崩壊してしまう・・・
そんな日は、そう遠くはないかもしれません。
絶滅の進行を遅らせる方法は身近なことかでも生物多様性を守る取り組みをすることができます、生物多様性の3つの要素を意識して小さなことでも出来ることを考えてみましょう。
まとめ
生物多様性には「生態系の多様性」「種の多様性」「遺伝子の多様性」の3つの多様性があり、過去50年間で約73%も失われた今、それぞれを守ることが大切です。
RECIPE×SDGs
生物多様性との関わりって?
生物多様性が失われることでで私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか。

海の豊かさは生活の豊かさ
海の生物多様性の影響を特に受けるのは海の幸ですね。2050年には海にいる魚の重さよりも海洋プラスチックごみが重くなるといわれています。そうなってしまえば、食卓に並ぶお魚を美味しく安全に食べられなくなってしまいます。

陸から世界の豊かさを守ろう
私たちが生活している陸地は地球表面の3割にも満たないといわれています。しかし、陸地での豊かさを失う行いは巡って海に行き、さらに巡って陸地にもどってきます。つまり、自分たちの悪い行いは巡り巡って戻ってくるということ。まずは自分の周りから世界を豊かにしていきましょう。


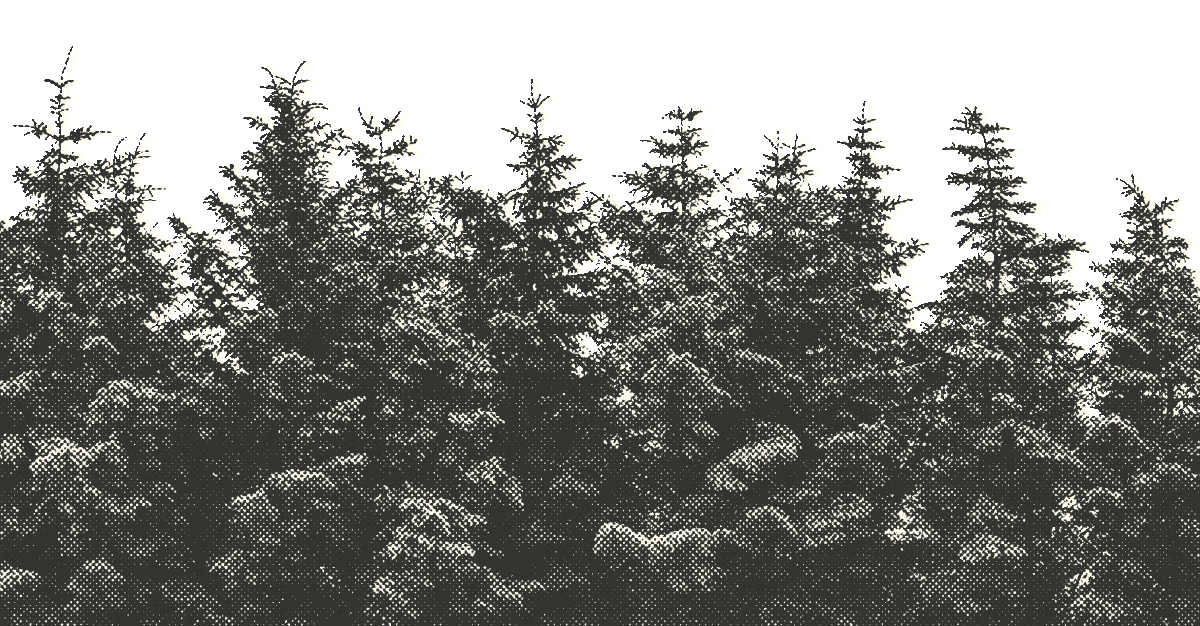

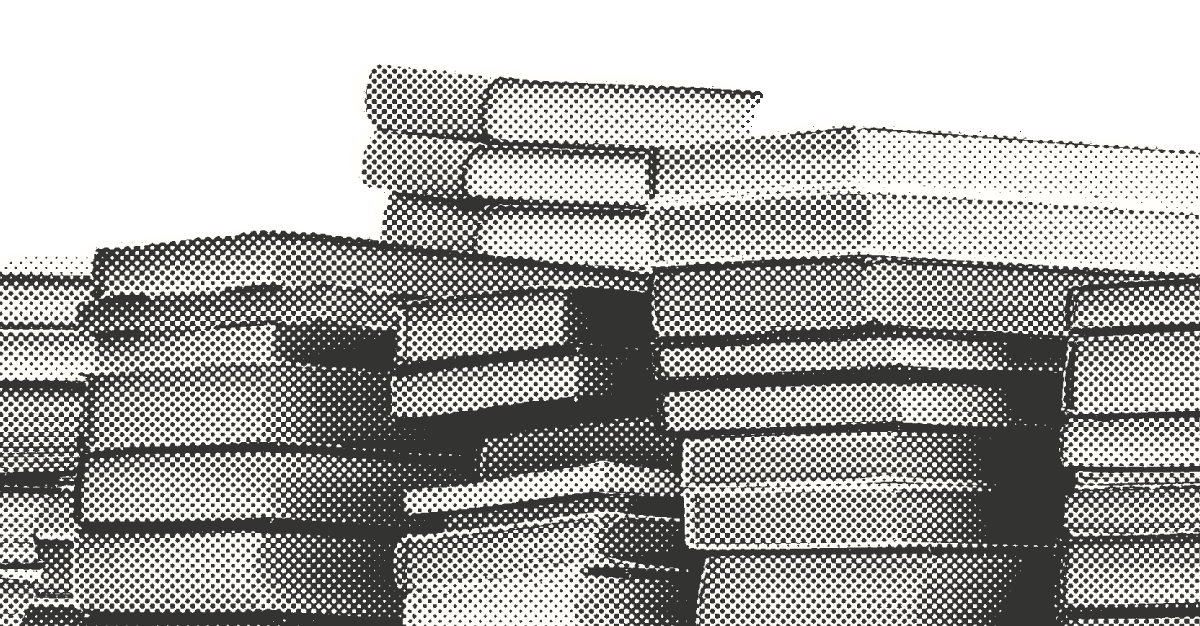
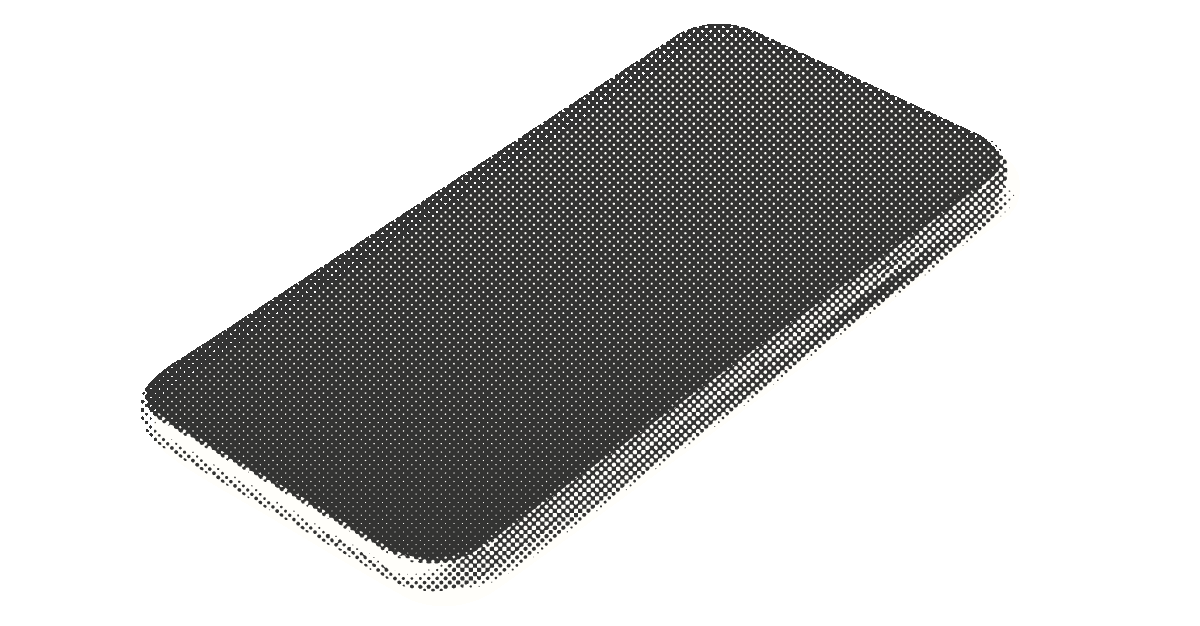
自由コメント
①レシピを読んであなたが思ったことや気になることをぜひ教えてください。
②生物多様性の3つの要素を意識することによって、どのようなことが見えましたか。
思ったことや気になることをぜひ教えてください。